トレーラー紹介
レビュー
*原則ネタバレを含まないようにレビューしていますが、ストーリーの流れや一部分の内容、撮影手法などへの言及を含むことがありますので、情報を入れずに観たいという方は、鑑賞後にお読みください。
原題は“Dead Poets Society”(死せる詩人の会)であり、邦題が「いまを生きる」でなければこの映画は日本では眠っていただろうし、私も手に取ることはなかったでしょう。
この映画は1959年のアメリカバーモント州を舞台にする。有名進学校ウェルトン校に来た新任教師のジョン・キーティングは、破天荒な授業で詩の本当の素晴らしさ、生きることの素晴らしさを生徒に教える。
原題の「死せる詩人の会」はキーティングがウェルトン校在学中に結成した読詩同好会で、そのことを知った生徒たちが自分たちの手で復活させることになる。しかし、ウェルトン校は四柱(伝統・名誉・規律・美徳)を重んじる学校であり、自由な発想や夢は幸福にはならないと先生も親も考えている。
学校や親に作られた道を歩むこと。すべて公式に当てはめたような答えを追い求めることが幸せな生き方だろうか。生徒がキーティングと出会い、自由な表現を考えたり、夢を見つけたり、恋をしたりして生徒の顔がイキイキとしていく様が微笑ましい。
このような教育はアメリカでも行われていたのかという驚きもあれば、一方で日本も子どもに答えを与える教育になっていないか、親や先生は子どもに自ら考えさせているか、物や情報を与えすぎていないか、大人であれ子どもであれ今の私たちが同じような危機に陥っていないか、この映画を通じて自分と自分の周りのことを考えさせられます。
映画の背景を読む
(1)「おお船長!我が船長よ」の詩の続きとは?
キーティングが生徒たちに質問する、リンカーンに捧ぐホイットマンの詩「おお船長!我が船長よ」の続きとは何でしょうか?
詩の一部を引用します。
O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
ああ船長!我が船長!恐ろしい旅は終わりました、
船はいくつもの嵐を抜け、求めたものは勝ち取った、
港は近く、鐘も、歓喜の声も聞こえる
皆が、この頑丈な船体を目で追っています、
なのに、ああ魂よ!魂!魂!
ああ流れる赤い血よ、
我が船長は甲板に横たわり、
冷たく命を落とすなんて
船長とはつまり南北戦争の北部を率いたエイブラハム・リンカーンのことです。しかし、彼はその直後暗殺されてしまう。リンカーンは奴隷解放宣言でも有名ですが、ウォルター・ホイットマンもまた奴隷制度廃止論者でした。劇中でその続きの内容が明らかにされなかったのは、この映画の結末に通じるところがあったからかもしれません。
ちなみにウォルター・ホイットマン (Walter Whitman, 1819-1892) は、アメリカの詩人。彼はそれまでの伝統的な詩の技法に捉われず「自由詩の父」とも言われます。
(2)「処女たちへ」から学ぶこととは?
「処女たちへ」は、イギリス詩人ロバート・ヘリックの詩”To the Virgins, to Make Much of Time”です。
「今日咲き誇る花も 明日は枯れる」
「バラのつぼみは早く摘め」はラテン語で「カーぺ・ディエム」。つまり「いまを生きろ」ということ。我々はいずれ死ぬ運命であり、ここにいる全員がいつか息が止まる日が来て冷たくなって死ぬのである。
若さとは価値であり、その価値を無駄にしないこと。歳を取ってからではできないことが増えてくる。自然と制限がかかってくるのである。そのことを1日でも若い時に気付くこと。カーぺ・ディエム!!
(3)私たちにとっての「詩」とは何か?
学者は詩を数値で測ろうとする。これは戦争であり、それは私たちの心や魂の危機。自分の力で考えることを学ぶのだ。言葉や表現を味わうことを学ぶ。言葉や理念は世の中を変えられる。我々はなぜ詩を読み書くのか。それは我々が人間であるという証。そして人間は情熱に満ちあふれている。詩や美しさ、ロマンス、愛こそは我々の生きる糧だ。
「信仰なき者の長い列」
「愚か者に満ちた都会」
「何の取り柄があろう 私よ命よ」
「答え・・・それは君がここにいること」
「命が存在し 自己があるということ」
「力強い劇は続き 君も詩を寄せることができる」
キーランドの言葉を引用しましたが、「詩を寄せる」とはどういうことか自分自身で考えてみましょう。
(4)机の上に立ち、生徒に伝えたいこととは?
それは物事を常に異なる側面から見つめるため。分かっていることも別の面から見直すことによって新しい考えが見つかる。それがどんなにバカらしく思えてもやってみよう。本を読む時は作者の意図より自分の考えを大切に。自ら自分の声を見つけなくてはいけない。
「人は静かな絶望に生きる」とはアメリカの詩人ヘンリー・デイヴィッド・ソローの言葉。勝手に自分の限界や枠組みを作るのではない。「静かな絶望に生きる」とは、大きな喜びも感動もなければ、大きな失望もない生き方であり、生きた証すら残らない。そんな生き方でいいの?という問いかけである。
(5)この映画のロケ地はどこ?
アメリカデラウェア州にあるセント・アンドリューズ・スクールです。昔は男子校でしたが、今は共学の学校です。
外の風景はとてものどかで、こんなところに老後住めたらいいなぁと思いますね。
この映画を観て学べること
この映画は、画一的な社会の中で個性を大切にしながら生きることの意味と困難さを描いた、青春映画の枠を超えた普遍的なメッセージを持つ作品です。特に教育に携わる人や、自分らしい生き方を模索している人にとって、多くの示唆を与えてくれます。
キーティング先生の自由で創造的な授業は、暗記や規則に縛られた従来の教育方法とは対照的です。生徒一人ひとりの個性や感性を引き出すことの大切さ、知識を生きた智恵として活用することの重要性を教えてくれます。
また、人生は有限であり、今この瞬間を大切に生きることの意味を深く考えさせられます。将来への不安や過去への後悔にとらわれるのではなく、現在に集中して生きることの価値を示しています。
さらに、詩を通して生徒たちが自分の内なる声を発見していく過程が描かれます。他人の期待や社会の枠組みに従うだけでなく、自分らしい表現や生き方を見つけることの重要性を教えてくれます。
その他、伝統や権威を盲目的に受け入れるのではなく、批判的に考える力の大切さや、夢を追いながらも、現実と向き合い、周囲との関係を築いていくことの難しさと重要性、生徒の可能性を引き出す真の教育とは何かについて考えさせられます。
この映画を観た後に読みたい本
教育・学習論に関する書籍
『学びとは何か』(今井むつみ著)は、真の学習とは何かについて認知科学の観点から解説しており、暗記型教育への批判的視点を深められます。
『「学力」の経済学』(中室牧子著)では、データに基づいた教育効果について考察されています。
創造性・思考力に関する書籍
『考える技術・書く技術』(バーバラ・ミント著)は、論理的思考と表現力について実践的に学べます。
現代の教育問題に関する書籍
『教育格差』(松岡亮二著)では、日本の教育制度の問題点について社会学的に分析されています。
『ブラック校則』(内田良著)は、学校の規則や管理体制について批判的に考察しています。
コーチング・人材育成に関する書籍
『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』(マーシャル・ゴールドスミス著)では、人の可能性を引き出す方法について具体的に書かれています。『学習する組織』入門版(ピーター・センゲ著)も参考になります。
哲学・人生論に関する書籍
『君たちはどう生きるか』(吉野源三郎著)は、若者が自分なりの価値観を築くための古典的名著です。
『人生の意味の心理学』(アルフレッド・アドラー著)では、自分らしい生き方について深く考察されています。
表現・コミュニケーションに関する書籍
『伝える力』(池上彰著)では、自分の考えを効果的に表現する方法について学べます。
『人を動かす』(デール・カーネギー著)は、人間関係とコミュニケーションの古典です。
批判的思考に関する書籍
『クリティカル進化論』(道田泰司著)では、物事を批判的に考える力の育成について書かれています。
現代社会論に関する書籍
『同調圧力』(鴻上尚史著)では、日本社会の同調圧力について分析されており、個性を大切にすることの難しさを理解できます。
基本情報
原題:Dead Poets Society
ジャンル:ヒューマン
公開:1989年(アメリカ)1990年(日本)
時間:2時間8分
監督:ピーター・ウィアー
出演:ロビン・ウィリアムズ、ロバート・ショーン・レナード、イーサン・ホーク
興行収入:$235,860,116
“Two roads diverged in a wood and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference.” Robert Frost
「森の中で道が二手に分かれていて、私は、私は人があまり通っていない方の道を選んだ。それがすべてを変えた。」
ロバート・フロスト
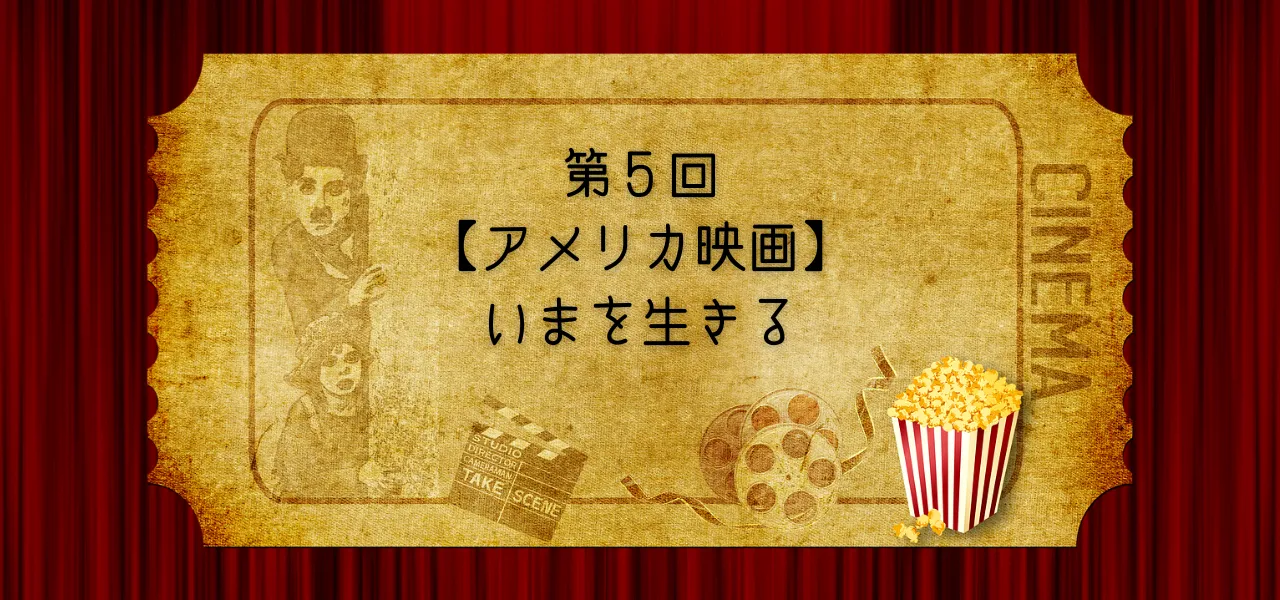
![いまを生きる [ ロビン・ウィリアムズ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0712/4959241930712.jpg?_ex=128x128)
![学びとは何か 〈探究人〉になるために (岩波新書 新赤版1596) [ 今井 むつみ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5964/9784004315964.jpg?_ex=128x128)
![「学力」の経済学 [ 中室 牧子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0579/9784799330579_1_3.jpg?_ex=128x128)
![考える技術・書く技術新版 問題解決力を伸ばすピラミッド原則 [ バーバラ・ミント ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0273/9784478490273.jpg?_ex=128x128)
![教育格差 階層・地域・学歴 (ちくま新書 1422) [ 松岡 亮二 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2375/9784480072375_1_254.jpg?_ex=128x128)
![ブラック校則 理不尽な苦しみの現実 [ 荻上チキ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5574/9784491035574.jpg?_ex=128x128)
![コーチングの神様が教える 「できる人」の法則 (日経ビジネス人文庫) [ マーシャル・ゴールドスミス ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9226/9784296119226_1_7.jpg?_ex=128x128)
![学習する組織 システム思考で未来を創造する [ ピーター・M.センゲ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1019/9784862761019.jpg?_ex=128x128)
![君たちはどう生きるか [ 吉野源三郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9463/9784838729463_1_7.jpg?_ex=128x128)
![漫画 君たちはどう生きるか [ 吉野源三郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9470/9784838729470_1_3.jpg?_ex=128x128)
![人生の意味の心理学〈新装版〉 (アドラー・セレクション) [ アルフレッド・アドラー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6864/9784434296864_1_3.jpg?_ex=128x128)
![「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える! 伝える力 (PHPビジネス新書) [ 池上 彰 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0810/9784569690810.jpg?_ex=128x128)
![人を動かす 改訂文庫版 [ D・カーネギー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1347/9784422101347_1_5.jpg?_ex=128x128)
![クリティカル進化論 『OL進化論』で学ぶ思考の技法 [ 道田 泰司 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7628/76282139.jpg?_ex=128x128)
![同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書) [ 鴻上 尚史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6621/9784065206621.jpg?_ex=128x128)
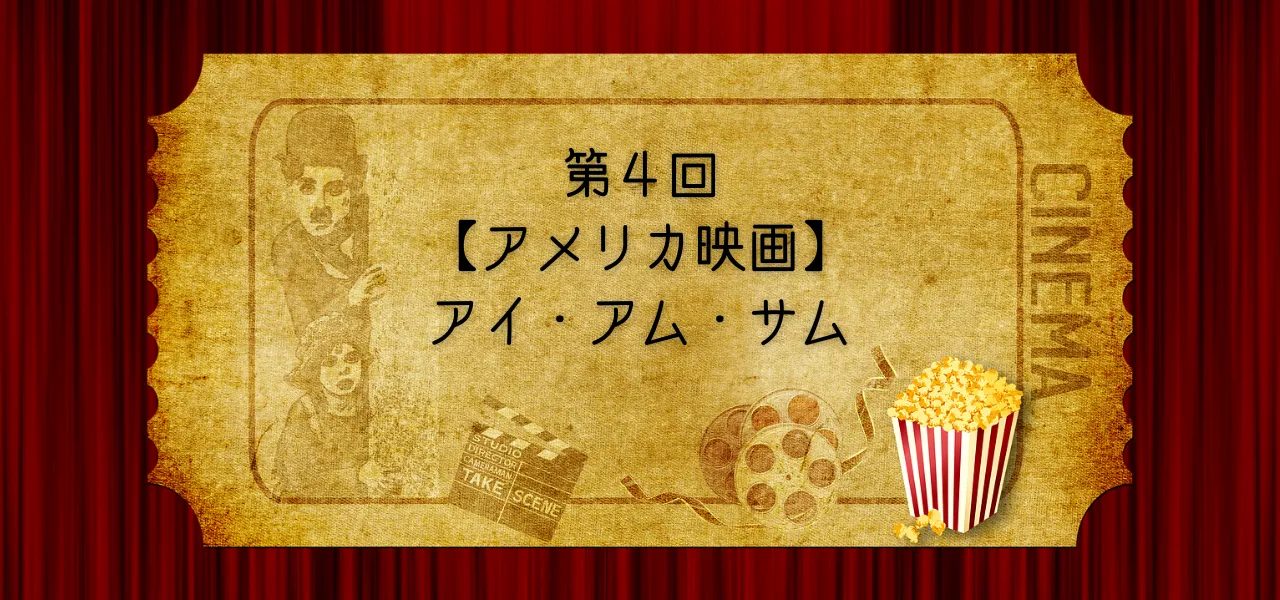

コメント