トレーラー紹介
レビュー
*原則ネタバレを含まないようにレビューしていますが、ストーリーの流れや一部分の内容、撮影手法などへの言及を含むことがありますので、情報を入れずに観たいという方は、鑑賞後にお読みください。
クリスマスシーズンに家族や友達と楽しめる不朽の名作映画。本作はモノクロですが、2006年に『三十四丁目の奇蹟 スペシャル・カラー・バージョン』としてカラーライズされています。また、リメイク版『34丁目の奇跡』も1994年に製作されています。
クリスマス映画で色がないのは味がないのですが、個人的には1947年という時代に作られた原作を観て、頭の中で赤色や緑色を想像することが本作のメッセージにも通じるところがあるため、モノクロ版で観ることをお勧めします。
舞台はニューヨーク、マンハッタン34丁目にある百貨店メイシーズ。クリスマス商戦の開始を告げるクリスマスパレードに、クリス・クリングル(サンタクロースの別名)を名乗る老人がパレードサンタの代役を務めるところから物語は始まる。
クリスはメイシーズで働くことになるが、自分のことを本当のサンタクロースであるという彼にメイシーズの精神科医ソーヤーは訝しみ、侮辱されたことへの恨みから彼のことを精神病棟に入れようとする。
彼のことを擁護する弁護士のフレッドが審問の申し立てをかけ、
サンタクロースが法廷に立つという状況になり・・・。
サンタクロースは存在するのか?という問いから、その背景にいる子どもたちやその親、クリスマス商戦にかける百貨店関係者の人間関係も映し出し、常識を抜きにした「信じること」の大切を伝える映画です。
劇中弁護士フレッドと主演ドリス(メイシーズ人事)との会話が核心をついています。
フレッド「この裁判で彼は優しさや愛、無形の財産を象徴している」
ドリス「子どもみたいなことを。現実の世界では通用しないの。成功しないわ」
フレッド「それは成功をどう定義するかによる。現実社会に対する君の考えが通用しなくなったら、無形の財産に気づくはず。その時、価値が分かるよ。」
映画の背景を読む
(1)百貨店メイシーズは実在する?
メイシーズ (Macy’s) は、アメリカ合衆国ニューヨークに本部がある百貨店で実在します。1851年に、ローランド・ハッシー・メイシーが創業。1858年にニューヨークへ移転、マンハッタン6番街14丁目にニューヨーク最初の店舗を構えます。ブロードウェーと34丁目角のヘラルド・スクエアへ移転したのは1902年のこと。近年はアマゾンなどのネット販売に押され、1万人超のリストラ、店舗閉鎖が続く。
(2)子役スーザン・ウォーカーについて
この映画は1947年に公開されているので、登場する俳優女優はほとんどお亡くなりになられています。そこで目がいくのが子役スーザン(ナタリー・ウッド)です。この映画で人気スターとなり、1955年『理由なき反抗』でアカデミー助演女優賞にノミネート。西部劇『捜索者』、ミュージカル映画『ウエスト・サイド物語』、青春映画『草原の輝き』などに出演しています。
しかし、ナタリー・ウッドは43歳で謎の死を遂げています。映画『ブレインストーム』撮影中にロサンゼルス沖で行方不明になり、翌日水死体となって発見されました。事故死とされた一方殺されたという意見もあり、近年まで捜査が行われているが、真相は分かっていません。
(3)マティーニとはどんなお酒?
マティーニは、ジンとベルモットをベースに作られるショートカクテルで、カクテルの王様とも呼ばれています。カクテルには「ロング」と「ショート」があり、ショートカクテルは氷を入れずに飲むのが特徴です。度数は約35%。マティーニのグラスの中にはオリーブが入っていることも特徴。マティーニはジェームズ・ボンドの影響で世界中に広まったことで有名です。

(4)サンタクロースのトナカイたち
オープニングでクリスがショップ店員のトナカイの並べ方について指摘するシーン。「キューピッドとブリッツェンの位置が逆、それにダッシャーは私の右側だ、ドナーの枝角は4本」と言っていますが、順番があるのでしょうか?
 出典:flickr:At the Macy’s Thanksgiving Day Parade.(https://www.flickr.com/photos/19982106@N00/3069246957)、tweber1
出典:flickr:At the Macy’s Thanksgiving Day Parade.(https://www.flickr.com/photos/19982106@N00/3069246957)、tweber1
1823年、ニューヨークの神学者クレメント・クラーク・ムーアによる子供向けの詩『クリスマスのまえのばん』(A Visit from St. Nicholas)によると、サンタクロースは口笛を吹いて8頭のトナカイを「ダッシャー、ダンサー、プランサー、ヴィクセン、コメット、キューピッド、ドナー、ブリッツェン」と呼び、早く走るよう元気づけています。
作り物の順番や特徴にも気を配るあたり、やはりクリスは本物のサンタクロースなのかもしれませんね。
(5)リメイク版『34丁目の奇跡』
1994年製作『34丁目の奇跡』は本作のリメイクです。監督はレス・メイフィールド、出演はリチャード・アッテンボローとマーラ・ウィルソンなどです。
この映画を観て学べること
この映画は、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさの価値を説き、人間の善意と信頼の力を信じることの大切さを伝える不朽の名作です。
サンタクロースの存在を信じるクリス・クリングルを通じて、大人になっても失ってはいけない純粋な信念の大切さを描いています。現実主義に偏りがちな現代社会において、想像力や夢を持つことの価値を再認識させてくれます。
また、ドリスは娘のスーザンに現実的な教育を施そうとしますが、完全な懐疑主義では人生の豊かさを失うことを学びます。健全な懐疑心を持ちながらも、時には信頼することの重要性を示しています。
クリスが精神的な問題を抱えているとみなされる場面では、社会の偏見や先入観によって個人が不当に扱われることの問題を提起しています。真の人格は外見や社会的地位ではなく、行動によって判断されるべきだという教訓があります。
さらに、デパートを舞台にしながら、純粋な善意が商業的利益よりも価値があることを描いています。メイシーズとギンベルズの競争関係を超えた協力は、ビジネスにおける倫理的な在り方を問いかけます。
そして離婚を経験したドリスとスーザンが、フレッドとクリスとの出会いを通じて新しい家族の形を見つけていく過程は、愛と信頼に基づく真の家族関係の大切さを教えてくれます。また、法廷シーンでは、法的な証明と道徳的真実の違いが描かれ、正義とは何かという根本的な問いを投げかけています。
この映画を観た後に読みたい本
クリスマス映画・文化論に関する書籍
『クリスマスの文化史』(若林ひとみ著)では、西洋におけるクリスマスの社会的・文化的意味を詳細に分析しており、この映画が描くクリスマス精神の背景を理解できます。
アメリカ映画史・古典ハリウッドに関する書籍
『ハリウッド映画史講義 翳りの時代の光と影』(蓮實重彦著)は、1940年代のハリウッド映画の特徴と社会的背景を詳しく解説しており、「三十四丁目の奇蹟」が制作された時代の文脈を理解するのに有用です。
『アメリカ映画史入門』(杉野健太郎著)は、1940年代を含むアメリカ映画史を体系的に学べる最新の研究書です。
家族映画・アメリカ文化論に関する書籍
『ハリウッド100年史講義』(北野圭介著)は、アメリカ映画の変遷を通じて社会の変化を読み解く名著で、1940年代の家族観についても詳しく解説されています。
『アメリカ映画の文化副読本』(渡辺将人著)は、アメリカ映画を通じてアメリカ文化を理解するための現代的な入門書です。
『見て学ぶアメリカ文化とイギリス文化』(藤枝善之著)は、映画を通じてアメリカ文化を理解するための実践的な書籍です。
宗教・信仰と映画に関する書籍
『映画で読むキリスト教』(栗林輝夫著)では、ハリウッド映画におけるキリスト教的価値観の描かれ方が分析されています。
基本情報
原題:Miracle on 34th Street
ジャンル:ファンタジー、クリスマス
公開:1947年(アメリカ)1948年(日本)
時間:1時間36分
監督:ジョージ・シートン
出演:モーリン・オハラ、ジョン・ペイン、エドマンド・グウェン
信じていれば常識は問題じゃない。物事が思い通りにいかなくても、相手を信じることを私は知ったの。
ドリス・ウォーカー(モーリン・オハラ)
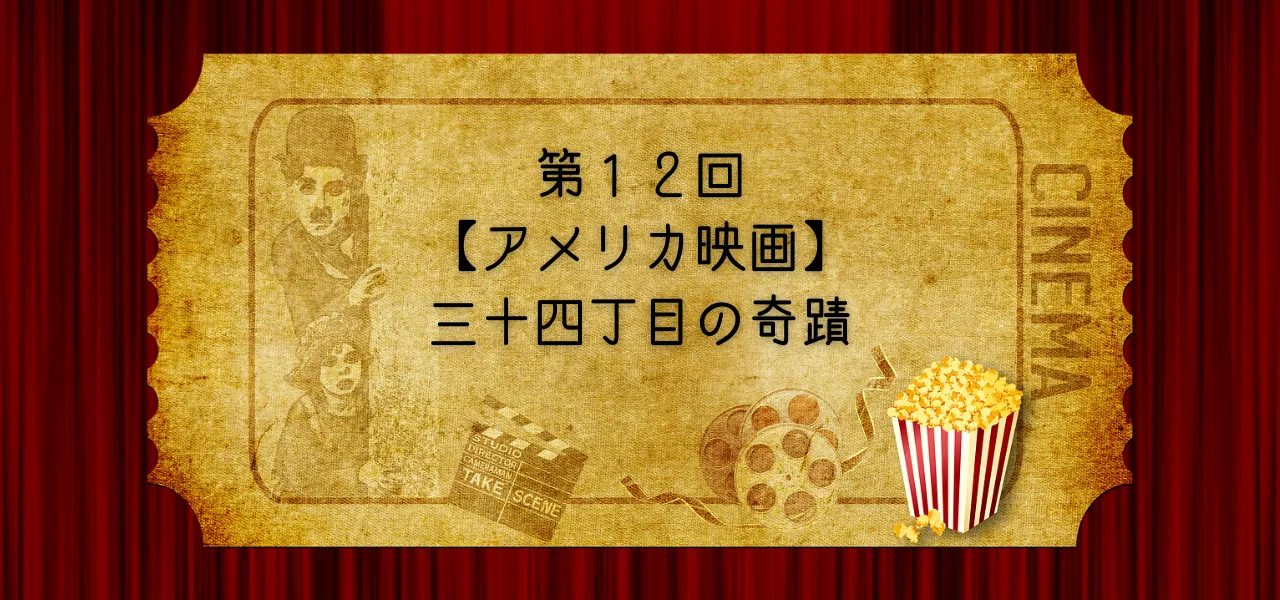


![34丁目の奇跡 [ リチャード・アッテンボロー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5527/4988142925527.jpg?_ex=128x128)
![クリスマスの文化史新装版 [ 若林ひとみ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1044/9784560081044.jpg?_ex=128x128)
![ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために (ちくま学芸文庫) [ 蓮實 重彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8283/9784480098283_1_91.jpg?_ex=128x128)
![アメリカ映画史入門 [ 杉野健太郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0379/9784384060379_1_4.jpg?_ex=128x128)
![新版 ハリウッド100年史講義 夢の工場から夢の王国へ (平凡社新書) [ 北野 圭介 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8495/9784582858495.jpg?_ex=128x128)
![アメリカ映画の文化副読本 [ 渡辺将人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9479/9784296119479_1_6.jpg?_ex=128x128)

![シネマで読むアメリカの歴史と宗教[本/雑誌] (単行本・ムック) / 栗林輝夫/共著 大宮有博/共著 長石美和/共著](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_765/neobk-1542224.jpg?_ex=128x128)
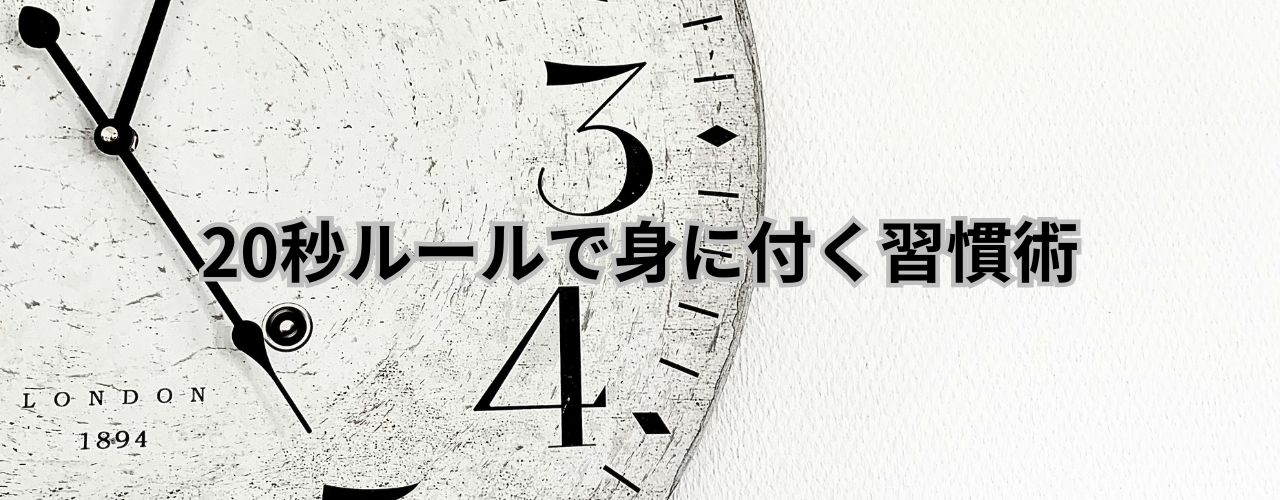
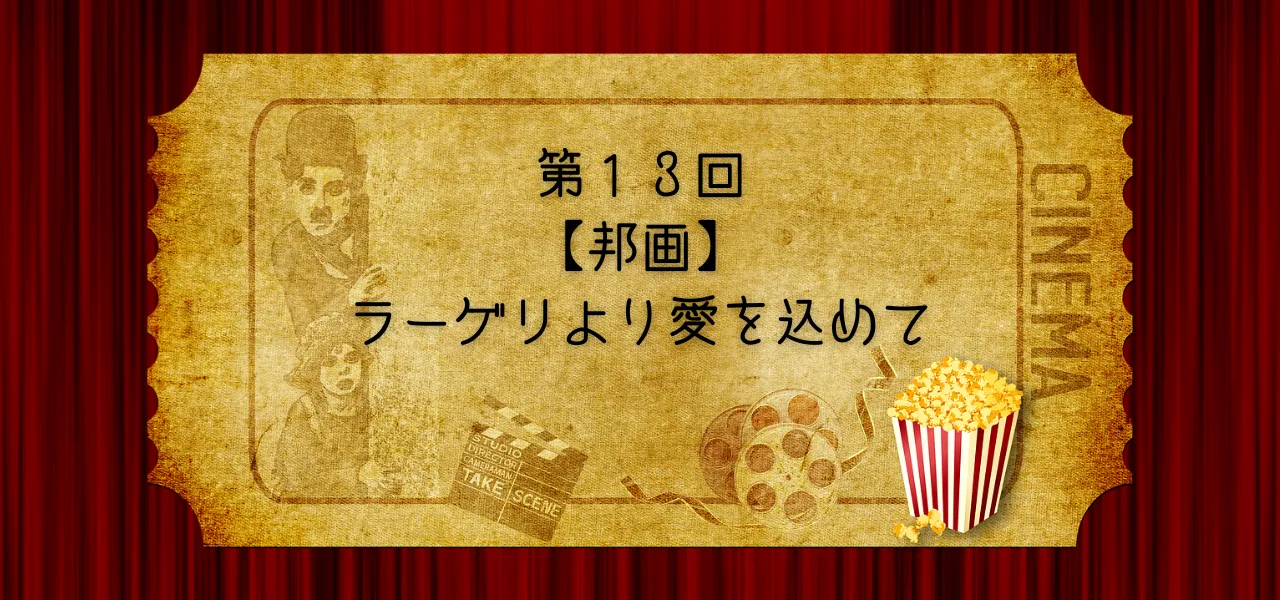
コメント