トレーラー紹介
レビュー
*原則ネタバレを含まないようにレビューしていますが、ストーリーの流れや一部分の内容、撮影手法などへの言及を含むことがありますので、情報を入れずに観たいという方は、鑑賞後にお読みください。
電車が到着時刻より早く着いたということだけで、駅のホームで踊るインドの人達の動画を最近見ましたが、歌と踊りはインド人の日常生活から切り離すことはできないんですね。世界の映画製作本数では圧倒的1位のインド映画が日本で上映されないのは、時間が長過ぎるからかもしれません。
そしてこの映画ももれなく歌と踊りがあるインド映画ゆえ、3時間近くありますが、個人的には全く長さを感じさせませんでした。さらに続きがあるなら是非観たいと思うほど楽しい映画です。スティーヴン・スピルバーグは「3回も観るほど大好きだ」と絶賛、ブラッド・ピットも「心震えた」とコメントしているほどの映画です。
ランチョーの言葉
この映画まずはアーミル・カーン演じるランチョー(フルネームはランチョルダース・シャマルダース・チャンチャル)がとにかくカッコよすぎる!彼は当時44歳で大学生に見えるほど容貌もかっこいいのですが、社会のレールに乗ることなく自由に生きるその姿がとても魅力的です。そして劇中には深く考えされられるランチョーの言葉がいくつもあります。
「なぜ私が試験で一番か分かるか?工学に情熱があるからだ。」
周りはいい点を取ろうと競争しているが、ランチョーは好きだから勉強していると言うのです。ランチョーにとって勉強はいつも楽しいものなのでしょう。
「成功ではなく優秀さを追求しろ。成功は自ずとついてくる」
上の言葉に通じるところがありますが、好きなことに没頭することが学びになり、結果として成功につながると言っています。テストでいい点を取ること、いい就職先に内定をもらうこと、金持ちになるといった「成功」をハナから追い求めるな、ということですね。
「うまーくいーく」
簡単には覆せないかもしれない困難に遭遇した時にランチョーがいつも発する言葉です。人の心はとても臆病だから、困難に立ち向かうときはそれをマヒさせる必要がある、と言います。この言葉は神頼みにしようとしているのではなく、自分自身の感情をうまーくコントロールしているんですね。
チャトルの存在
ランチョーと対極のキャラクターとしてチャトル・ラーマリンガム(通称サイレンサー)が描かれますが、彼の生き方こそ社会が追い求めている生き方であることを忘れてはいけません。卒業10年後には大会社の副社長で経済的にも「成功」しているわけですからね。社会のレールに乗った生き方もある、ランチョーのような生き方もある。あなたが心を充実させ幸せになるために、どちらの生き方を選びますか?と観客には問われているのです。
映画のポイント
さて、この物語のターニングポイントは、卒業後身をくらませたランチョーは実在せず別の人物だった、ということです。学生時代に仲の良かったファルハーンとラージュー、そしてチャトルが「ランチョー」に会うためにドタバタしながら彼の居場所を突き止め、その先で見た光景はとても美しいものでした。
映画の背景を読む
(1)超難関理系大学ICEは実在する?難易度は?
ICE工科大は架空の大学ですが、インドにはインド工科大学(IIT=Indian Institute of Technology)が国内に23校あります(2022年現在)。ちなみに製作された2009年時点では15校だったのでますます「IITブランド」が確立されています。その中でもインド最高峰の大学は、インド工科大学マドラス校。IITの入試倍率は50倍以上とも言われ、世界で見ても難易度が非常に高い大学です。世界の大学ランキング2022(Times Higher Education)では200位にすら入っていませんが、資金力や教員数、留学生が少ないことで評価が欧米の大学に劣ります。
(2)インドは自殺率が高いのか?
2019年の調査でインドの自殺死亡率は、12.7(人口10万人当たり)で世界39位です。ちなみに映画製作年に近い2010年では16.5、2005年では17.6でしたから高水準でした。近年でこそインドの自殺率は減少傾向にあります。2019年度日本は15.3(25位)、中国は8.1(81位)、韓国は28.6(4位)です。インドの自殺率減少の理由はネットで調べても明確には記されていませんが、大学進学率がここ10年で20%を超え増加し続けていますし、教育設備が整ってきたことは一つの要因かもしれません。韓国も学歴社会で子どもはすごく勉強しますし、家族の期待がプレッシャーになり命を絶ってしまう子どもも多いと聞きます。明るい未来を作るはずの教育が子どもを苦しめることにならない社会を望みます。
(3)小便で人を感電させることができるのか?
可能です。
2014年9月、スペインのマヨルカ島で、立ち小便をしていた18歳の男性が感電による心肺停止で死亡した事件があります。彼の立ち小便をした足元には、敷設中の街灯の電力ケーブルが横たわっていました。電力ケーブルの上に尿がかけられ感電が引き起こされたのです。
尿の成分は84~85%が水分で残りが固形成分。最も多いのが尿素で塩分、クレアチン、尿酸などが含まれています。小学校の理科の授業で、水はほとんど電気を通さないけれど、食塩水にしたら水の中にイオンができて豆電球に電気が点く実験をしましたよね。
(4)カッコウは本当に他の鳥の卵を落とすのか?
カッコウは春になると南からやってくる渡鳥です。カッコウは他の鳥の巣に卵を産みつけ、他の鳥に雛を育てさせます。これを「托卵(たくらん)」といいます。カッコウの雛は他の鳥より早く孵化し、同じ巣の中の卵を自分の背中に乗せて、巣から落としてしまうのです。
(5)最後のシーンの舞台はどこ?
インドのパンゴン湖です。天空の湖とも呼ばれ、富士山より高い場所にあります。場所はインドの北部にあり湖は中国の国境を跨いでいます。面積は約600平方キロメートルもあります。
この映画は、インド教育制度への批判と人生の価値観について深く考えさせられる作品です。
この映画を観て学べること
この映画は、暗記中心の詰め込み教育ではなく、理解し応用する力の大切さを描いています。ランチョーが「理解せずに暗記することは意味がない」と示すように、本質を理解することの重要性を教えてくれます。成績や順位だけで人を評価するインドの教育システムの問題点も浮き彫りにしています。
また、周囲の期待や社会的な成功の定義に縛られず、自分の情熱や興味に従って生きることの大切さ、そして、どんな困難な状況でもポジティブに考えることの大切さが映画のタイトルからも伝わってくるでしょう。
この映画を観た後に読みたい本
教育・学習に関する書籍
『学習する組織』(ピーター・センゲ著)では、真の学習とは何かについて深く掘り下げています。
『マインドセット』(キャロル・ドゥエック著)は、成長思考と固定思考の違いを通して、学習への取り組み方を変える視点を提供してくれます。
創造性・イノベーションに関する書籍
『イノベーションのジレンマ』(クレイトン・クリステンセン著)は、既存の枠組みにとらわれない思考の重要性を示しています。
『クリエイティブ・マインドセット』(デイヴィッド・ケリー、トム・ケリー著)では、誰もが持つ創造性を引き出す方法について書かれています。
自分らしい生き方に関する書籍
『7つの習慣』(スティーブン・コヴィー著)は、他人の期待ではなく自分の価値観に基づいた生き方を説いています。
『ライフシフト』(リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著)では、長寿化社会での新しいキャリア観について考察されています。
ポジティブ心理学に関する書籍
『フロー体験』(ミハイ・チクセントミハイ著)では、真の充実感を得られる状態について科学的に分析されており、映画で描かれた「情熱を追求する」ことの意味がより深く理解できます。
基本情報
原題:3 Idiots
ジャンル:学園コメディ
製作:2009年
時間:2時間51分
監督:ラージクマール・ヒラニ
出演:アーミル・カーン、カリーナ・カプール
受賞歴:第37回日本アカデミー賞(2014年)
製作費:約5億8000万円
興行収入:約64億5000万円(日本1億5000万円)
未来を心配しすぎたら、今がなくなるだろう?
ランチョルダース・シャマルダース・チャンチャル
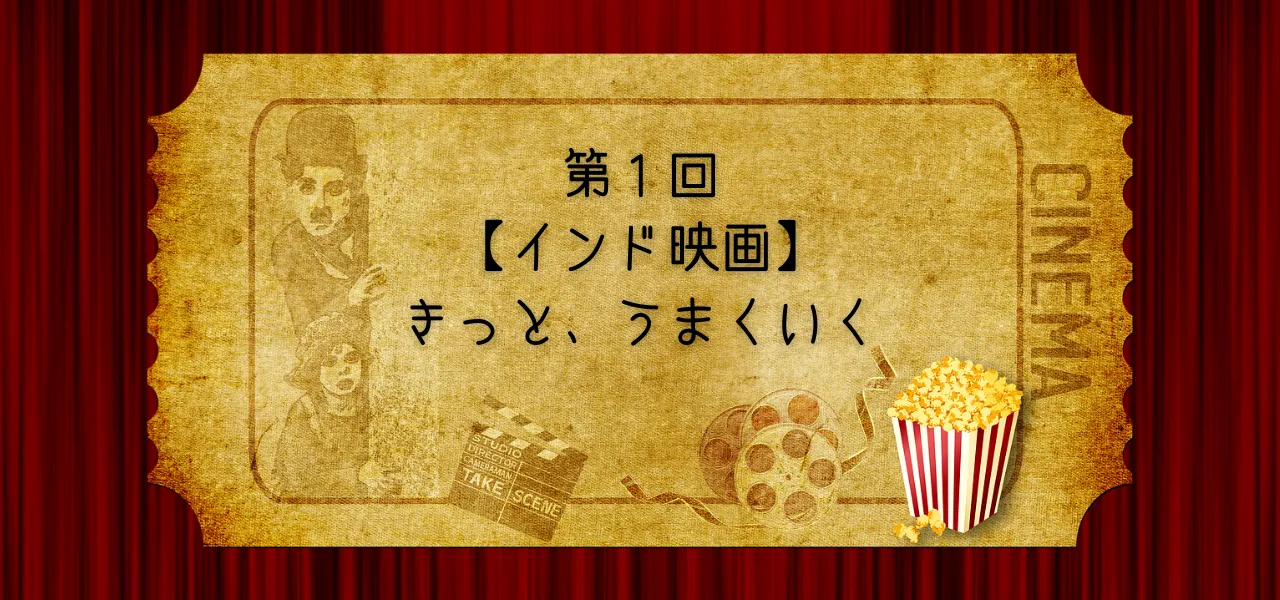
![きっと、うまくいく [ アーミル・カーン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0526/4907953040526.jpg?_ex=128x128)
![学習する組織 システム思考で未来を創造する [ ピーター・M.センゲ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1019/9784862761019.jpg?_ex=128x128)
![マインドセット 「やればできる!」の研究 [ キャロル・S・ドゥエック ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1780/9784794221780.jpg?_ex=128x128)
![イノベーションのジレンマ増補改訂版 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき (Harvard business school press) [ クレイトン・M.クリステンセン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0234/9784798100234_1_2.jpg?_ex=128x128)
![クリエイティブ・マインドセット 想像力・好奇心・勇気が目覚める驚異の思考法 [ トム・ケリー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0256/9784822250256.jpg?_ex=128x128)
![完訳7つの習慣 人格主義の回復 [ スティーヴン・R.コヴィー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0246/9784863940246.jpg?_ex=128x128)
![LIFE SHIFT(ライフ・シフト) 100年時代の人生戦略 [ リンダ・グラットン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3871/9784492533871_1_3.jpg?_ex=128x128)
![フロー体験入門 楽しみと創造の心理学 [ ミハイ・チクセントミハイ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4798/9784790714798.jpg?_ex=128x128)
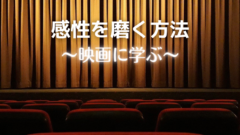
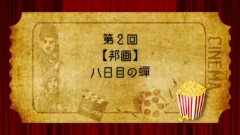
コメント