
あなたの寿命とあなたが勤めている会社の寿命はどちらが長いだろうか?東京商工リサーチの調査によると、2020年に倒産した企業の平均寿命は23.3年。もはや会社の商品のウリばかりを考える時代ではないですね。
・がむしゃらに働き続けている人
・入社4年目の社会人
・転職を考えている人
(推奨人数:2人以上〜偶数人数)
①二人組になる。
②順番に「あなたの商品は何ですか?」と聞く。
③あなたの会社の商品ではなくて、あなたの商品についてしつこく聞く。
④それがどういうもので、どういう値段で、どういう効用があるのかつっこみまくる。
⑤終わったら交代し、全員が終わったらみんなで結果を発表する。
1.ポイント:あなたの売りは何か
もしあなたが営業や接客をしていれば、お客様に会社の商品やサービスを売ることは日常茶飯事だろう。会社に入り3年くらいは、会社の商品やサービスを追求し、どのようにしたらその商品やサービスを売ることができるのか、知識やスキルを身につけながら考え抜かなればならない。
ある程度、売る力が身に付いてきた時に今回の「やってみよう!」をやってほしい。今まで売ってきた「会社の」商品やサービスは抜きにして、今度は「あなたの」商品やサービスは何かを考えてみましょう。
つまり、あなたを自身を売り込むことになったときに、あなたの「何を」「どのようなメリットで」「いくらで」買ってもらうのか、ということです。
2.必要な準備
特になし
・ノート
・ペン
3.参考例:スキルの需要を考える
あなたから会社の商品やサービスを奪ってしまったら、急にはしごを外された気分になるかもしれません。会社の中でも営業職ではなく経理やシステム部門などの専門職の方にはまだ簡単かもしれませんが、いざあなたのそのスキルや経験を買ってもらうためにどういうメリットがあるかすぐに答えることはできるでしょうか?
「ココナラ」というサービスを知っていますか?個人のスキル(得意)を売り買いできる日本最大級のスキルマーケットです。誰でも自分ができることを売ることができるプラットフォームです。
どういうスキルが売り買いされているのでしょうか?そのカテゴリを見てみましょう。
デザイン
イラスト・漫画
Webサイト制作・Webデザイン
音楽・ナレーション
動画・アニメーション・撮影
ビジネス代行・コンサル・士業
ライティング・翻訳
IT・プログラミング・開発
Webマーケティング・集客
占い
悩み相談・恋愛相談・話し相手
キャリア・就職・資格・学習
美容・ファッション・健康
ライフスタイル・エンタメ
オンラインレッスン・アドバイス
マネー・副業・アフィリエイト
弁護士検索・法律Q&A
出張撮影
ハウスクリーニング
これだけの大項目があり、さらにここから小項目に分かれます。え?こんなことまで買う人がいるの??と思われるかもしれませんが、この社会は需要と供給で成り立っています。困っている人がいるところには商売が生まれるのです。
こういうサービスも参考にしながら、自分の中に何か売れるものがないか、売れるものが見つかったらどれくらいの値段で売れるのか、他の人と比べてあなただけのメリットはあるか考えてみましょう。
4.まとめ
アテンション・エコノミー(*1)を提唱したアメリカの社会学者マイケル・ゴールドハーバー(Michael Goldhaber)によると、「これまでは無名でものんびり暮らせたが、これからはそうはいかない」と言っています。
情報化社会で誰もが情報を発信できるようになった現代、今までは東京やニューヨークという大都会に情報が集まり、会社という狭い箱の中が見えている世界の全てでした。それが自ら情報を取りに行くことができ、地球の裏側の情報まで知ることができます。そしてインフルエンサーという個人に、会社が頼る時代になりました。
会社の定年は65歳70歳と引き上げられ、20歳前後から働き始めても50年は働くことになります。しかし、30年以上続く会社は多くありません。思いもよらないパンデミックや大災害が起きて会社が成り行かなくなったらどうしますか?急に会社が整理解雇をし始めたらどうしますか?急に会社が潰れたらどうしますか?
あなたの売りを探しましょう。これからどんな世界になっても、自分の足で立てるように強い自分を作り、自分自身をブランド化しましょう!
(*1)Wikipedia アテンション・エコノミー
インターネットが発達した情報化社会においては、情報の優劣よりも「人々の関心・注目」という希少性こそが経済的価値を持つようになり、それ自体が重要視・目的化・資源化・交換財化されるようになるという実態を指摘した概念。
この記事を探求できるおすすめ書籍5選
『自分を最高値で売る方法』小林正弥
「何もない状態から1か月後に月収210万円を達成」という驚異的な実績を持つ著者による、自己ブランディングの決定版。この記事のテーマである「あなた自身の商品」「いくらで買ってもらうのか」を、具体的なメソッドで解説します。本書の核心は「自分の価値を高額で商品化する」という、この記事の「自分を自身を売り込む」というメッセージと一致する内容。「本業で実績を上げる」ことから始め、自分の強みを確立し、それを高額で購入してもらえるようになる方法が満載です。経営者や個人事業主だけでなく、副業として事業を行っている人、この記事の対象である「転職を考えている人」「入社4年目の社会人」にも最適。相手に価値を提供できるようになる具体的なステップが学べます。『パーソナルブランディング 最強のビジネスツール「自分ブランド」を作り出す』ピーター・モントヤ、ティム・ヴァンディー
パーソナルブランディングの古典的名著。この記事で触れている「あなたの『何を』『どのようなメリットで』『いくらで』買ってもらうのか」という3つの要素を、体系的に構築する方法を解説します。本書の特徴は、セルフブランディング=ぶれない芯を持つことという定義のもと、様々な業界・業種の人がどのようにパーソナルブランディングに成功するかを示している点。この記事の「ココナラ」のようなスキルマーケットで自分を売り込む際の理論的支柱となる内容です。営業活動をしなくても売り上げを安定させられる、ライバルとの差別化を図りオリジナリティを確立できる、人脈が広がり新たな仕事獲得につながるといった効果が期待できる実践書です。『トム・ピーターズのサラリーマン大逆襲作戦〈1〉ブランド人になれ!』トム・ピーターズ
この記事の参考文献として挙げられている、セルフブランディングのバイブル。経営思想家トム・ピーターズが1997年に「ブランド・ユー(Brand You)」という概念を提唱し、世界的ムーブメントを起こした歴史的名著です。この記事で触れている「会社の商品のウリばかりを考える時代ではない」「自分自身をブランド化しよう」というメッセージの源流がここにあります。「あなた株式会社のCEOになれ」という著者の主張は、この記事のテーマである「あなたの商品は何ですか?」という問いと一致。会社に頼らず自立して生きるための、時代を超えた本質的な考え方が学べます。『自分1人、1日でできる パーソナルブランディング』草間淳哉
タイトル通り、1人で1日で実践できるパーソナルブランディングの実践書。この記事のワークにある「あなたの商品は何ですか?」という問いに、具体的なフレームワークで答えを導き出す方法を解説します。本書の特徴は、難しい理論ではなく、今日からすぐに始められる実践的なアクションが満載である点。この記事で触れている「ココナラ」のようなスキルマーケットで自分のスキルを売る前に、まず「自分の強み」「提供できる価値」「ターゲット」を明確にする方法が学べます。フリーランスや個人事業主だけでなく、会社員として働きながら副業を考えている方にも最適。この記事の「自分自身をブランド化しましょう!」というメッセージを、最短距離で実現する一冊です。『個人力 やりたいことにわがままになるニューノーマルの働き方』澤円
元日本マイクロソフト業務執行役員で、プレゼンの神様と呼ばれる澤円さんによる、個人の時代の働き方を説いた一冊。この記事のテーマである「会社という狭い箱の中が見えている世界の全て」から脱却し、個人として価値を発揮する方法を解説します。本書の核心は「個人力=組織に頼らず自分で生きていく力」という定義で、この記事の「自分の足で立てるように強い自分を作る」というメッセージと一致。「会社の定年は65歳70歳と引き上げられ、50年は働くことになる」という記事の指摘を受け、どう生き抜くかを具体的に示します。コロナ後のニューノーマル時代に、個人としてどうブランド化し、価値を発揮していくかを学べる必読書です。参考文献
トム・ピーターズ『トム・ピーターズのサラリーマン大逆襲作戦〈1〉ブランド人になれ!』CCCメディアハウス、2000年
商売人はとくに約束を厳守することが必要である。時間を偽ったり、約束を破るような人はすぐ信用を失ってしまうのである。
浅野総一郎


![自分を最高値で売る方法 起業、副業、何でもいい! [ 小林正弥 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2282/9784295402282.jpg?_ex=128x128)
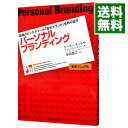
![ブランド人になれ! (Reinventing work series) [ トマス・J.ピーターズ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4840/48400307.jpg?_ex=128x128)
![自分1人、1日でできるパーソナルブランディング [ 草間淳哉 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9313/9784495539313.jpg?_ex=128x128)
![個人力 やりたいことにわがままになるニューノーマルの働き方 [ 澤円 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0271/9784833440271.jpg?_ex=128x128)
![トム・ピーターズのサラリーマン大逆襲作戦<1> ブランド人になれ! サラリーマン大逆襲作戦1ブランド人になれ【電子書籍】[ トム・ピーターズ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5324/2000005335324.jpg?_ex=128x128)
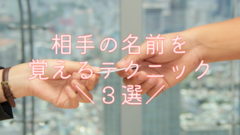
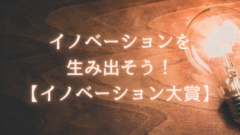
コメント