- トレーラー紹介
- レビュー
- 映画の背景を読む
- (1)劇中歌は誰の曲?
- オープニング曲「ダメダメのうた」(2000年) 作詞・作曲 – LADY Q/歌 – LADY Q & 野原しんのすけ、野原みさえ
- 挿入歌 「ケンとメリー 〜愛と風のように〜」(1972年) 作詞・作曲・編曲 – 高橋信之/歌 – バズ (20世紀博から帰る車内のシーン)
- 挿入歌「白い色は恋人の色」(1969年) 作詞 – 北山修/作曲 – 加藤和彦/歌 – ベッツィ&クリス (20世紀博内に作られた20世紀の街並みシーン)
- 挿入歌「聖なる泉」(1964年) 作詞・作曲 – 伊福部昭/歌 – ザ・ピーナッツ (ラジオから流れていた曲)
- 挿入歌「今日までそして明日から」(1971年) 作詞・作曲・歌 – よしだたくろう (20世紀博から家に帰る最後のシーン)
- エンディング「元気でいてね」(2001年) 作詞 – 白峰美津子/作曲・編曲 – 岩﨑元是/歌 – こばやしさちこ
- (2)大阪万博と大阪・関西万博の比較
- (3)「イエスタディ・ワンスモア」ケンとチャコの会話を振り返る
- (4)ひろしが欲しがった「迷子ワッペン」とは何か?
- (1)劇中歌は誰の曲?
- この映画を観て学べること
- この映画を観た後に読みたい本
- 基本情報
トレーラー紹介
出典:Youtube:「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」予告編(https://www.youtube.com/watch?v=5ei4d2vdLr4)、tvasahi
レビュー
*原則ネタバレを含まないようにレビューしていますが、ストーリーの流れや一部分の内容、撮影手法などへの言及を含むことがありますので、情報を入れずに観たいという方は、鑑賞後にお読みください。
本作はクレヨンしんちゃんの映画シリーズの中でも圧倒的な人気があり、ファンの間では「クレヨンしんちゃんの最高傑作」との呼び声も高い作品です。
一方で、監督の原恵一は「あの形で作るということに関して、『クレヨンしんちゃん』じゃ無くなるという自覚はあったが、それでもいい映画を作りたいという気持ちが勝ってあの形にした。」と語っており、相当な批判があったことも窺えます。
まず、この映画が子供向けかと問われると、親世代までターゲットにした作品であり、どちらかというと大人向けであることは間違いありません。
オープニングは1970年の大阪万博から始まり、20世紀の懐かしい思い出にはまっていく大人たちが描かれます。親たちに残されたかすかべ防衛隊(しんちゃん、トオルくん、ネネちゃん、マサオくん、ボーちゃん)は、幼児退行した大人たちを救うべく立ち上がり、「20世紀博」の創立者で「イエスタディ・ワンスモア」のリーダーであるケン、チャコと戦います。
ひろしの過去の回想シーンや、しんのすけが階段を駆け上がる描写は、昭和を知る大人たち、家族を持つ親たちに物凄く刺さることでしょう。
この作品は21世紀初めてのクレヨンしんちゃん劇場映画で、まさにこの公開タイミングだったからこそ、子どもを置き去りにしたり、子どもに運転させたりするシーンがまだ受け入れられたのかもしれません。90分もない映画でサクッと観れるわりには、過去や今の自分に投影して考えさせられるシーンが多く含まれています。
20世紀に描いていた未来とはどんなものだったのか?21世紀の今、20世紀に夢見た世界になっているのか?「あの頃はよかった」と思うことは少なくともありますが、今は過去には戻らないし、今から未来を作るのは私たちと私たちの子どもたちです。
クレヨンしんちゃんなんて子どもが観る映画でしょ?とか、あんな下品なアニメ子どもには観せられないとか、この映画を観るとクレヨンしんちゃんのイメージがきっと変わりますよ。
映画の背景を読む
(1)劇中歌は誰の曲?
20世紀の日本というテーマのため、昭和の曲が多く使われています。昭和の曲は曲調がゆっくりで大衆受けするように分かりやすく作られているのが特徴です。昭和の真っ只中を生きた世代には、その曲調からいろんな記憶が蘇ります。
オープニング曲「ダメダメのうた」(2000年) 作詞・作曲 – LADY Q/歌 – LADY Q & 野原しんのすけ、野原みさえ
出典:Youtube:ダメダメのうた(https://www.youtube.com/watch?v=bAAv2AkA6u4)、LADY Q – トピック
挿入歌 「ケンとメリー 〜愛と風のように〜」(1972年) 作詞・作曲・編曲 – 高橋信之/歌 – バズ (20世紀博から帰る車内のシーン)
出典:Youtube:Buzz / ケンとメリー ~愛と風のように~(https://www.youtube.com/watch?v=Eunqtuc7i-8)、8YASO
挿入歌「白い色は恋人の色」(1969年) 作詞 – 北山修/作曲 – 加藤和彦/歌 – ベッツィ&クリス (20世紀博内に作られた20世紀の街並みシーン)
出典:Youtube:白い色は恋人の色 – ベッツィー & クリス(https://www.youtube.com/watch?v=aF5ATASda74)、fkazz duffey
挿入歌「聖なる泉」(1964年) 作詞・作曲 – 伊福部昭/歌 – ザ・ピーナッツ (ラジオから流れていた曲)
出典:Youtube:聖なる泉 ザ・ピーナッツ(https://www.youtube.com/watch?v=IGQRkyUD-fo)、gogoyukke555
挿入歌「今日までそして明日から」(1971年) 作詞・作曲・歌 – よしだたくろう (20世紀博から家に帰る最後のシーン)
出典:Youtube:『今日までそして明日から』吉田拓郎(https://www.youtube.com/watch?v=6dLMWLhYXxQ)、Mikio Koide
エンディング「元気でいてね」(2001年) 作詞 – 白峰美津子/作曲・編曲 – 岩﨑元是/歌 – こばやしさちこ
出典:Youtube:[最高音質] 小林幸子 – 元気でいてね [オトナ帝国の逆襲](https://www.youtube.com/watch?v=lcPkPUwhaN8 )、桔梗刈萱
(2)大阪万博と大阪・関西万博の比較
みさえが劇中で大阪万博の来場者数「6,421万人」と言っています。では、2025年大阪・関西万博の来場者数は何人だったでしょうか?答えは「2,557万人」です。
この数字を見ると、当時の万博がいかに日本の人々に影響を与えたのか感じることができるでしょう。そのうちの1,650万人が見たとされるアメリカ館での「月の石」はアポロ計画の成果です。日本館では未来の乗り物として「リニアモーターカーの模型」が人気、ソ連館は宇宙開発の成果として「人工衛星や宇宙船」などが展示されていました。
「人類の進歩と調和」がテーマで77カ国の参加。では、今回の大阪・関西万博のテーマと参加国数は分かりますか?答えは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。
新型コロナウイルスの影響も踏まえ、一人ひとりが望む生き方を考え、誰もが可能性を最大限に発揮できる持続可能な社会を、世界全体で共創していくことを目指しています。参加国数は「158カ国」でした。
これらの数字から、昔と比べると私たちの世界はかなり狭くなったのかもしれません。今のようにIT技術はなく情報もない世界だからこそ、人々の夢や希望は大きく膨らんでいたのでしょう。
(3)「イエスタディ・ワンスモア」ケンとチャコの会話を振り返る
チャコ「ここに来るとほっとする」
ケン「ここには外の世界みたいに余計なものがないからな、昔外がこの町と同じ姿だったころ、人々は夢や希望に溢れていた。21世紀はあんなに輝いていたのに、今の日本に溢れているのは、汚い金と燃えないぐらいだ。これが本当にあの21世紀なのか。」
チャコ「外の人たちは心がからっぽだから、物で埋め合わせしているのよ。だからいらないものばっかり作って世界はどんどん醜くなっていく。」
ケン「もう一度、やり直さなければいけない。日本人がこの町の住人たちのように、まだ心を持って生きていたあの頃まで戻って。」
チャコ「未来が信じられたあの頃まで。」
家に帰る時の二人の会話に、21世紀の社会に対する不満や失望が表れています。2000年に至るまでの日本社会はどのような状況だったのでしょうか?
失業率は1990年代初頭の2%台から2002年には戦後最悪の5.4%まで上昇しています。特に若年層と中高年層で雇用情勢が厳しくなり、社会問題化していました。この頃、日本経済はいわゆる「失われた10年」と呼ばれる長期停滞に入り、企業は過剰な設備投資や不良債権の処理に追われ、新規採用を大幅に抑制しています。従来の「終身雇用」「年功序列」といった日本的雇用慣行が維持できなくなり、企業はリストラを本格化させました。また、1997年には山一證券や北海道拓殖銀行などの大手金融機関が相次いで破綻、金融システム不安が深刻化しています。
ここに至るまで、ケンやチャコの身にも何かしらの暗い過去があったのかもしれませんね。
(4)ひろしが欲しがった「迷子ワッペン」とは何か?
20世紀博内にある「エキスポ70」という大阪万博を再現した部屋があり、ひろしが子どもの頃に万博で見ることができなかった「月の石」を見ることができるチャンスということで、このワッペンを欲しがっています。当時の万博でも実際に配布されていて、会場の迷子を親と引き合わせるために番号が振られていました。
今回の大阪・関西万博でも「まいごリストバンド」というリストバンドが希望者に配布されています。裏面の照合番号を独自の端末に入力すると、親子が入場時に登録した名前や連絡先が表示される仕組みになっていました。
この映画を観て学べること
この映画の核心は、過去への執着と現在を生きることのバランスです。大人たちが昭和の懐かしい世界に取り込まれていく様子は、私たち自身が過去を美化しすぎることへの警鐘となっています。「あの頃は良かった」という思いに囚われすぎると、今この瞬間や未来への希望を見失ってしまう危険性を示しています。
また、ひろしの回想シーンは、多くの大人を感動させました。彼は懐かしい記憶に浸りながらも、最終的には「今ここにいる家族」のために立ち上がります。過去の自分も大切ですが、それ以上に現在の家族との絆や責任が重要だというメッセージが込められています。ひろしやみさえが歩んできた人生は、決して華やかではないかもしれません。しかし彼らが積み重ねてきた日常、子どもたちとの思い出、小さな幸せこそが、人生の本当の価値であることを教えてくれます。「平凡な日常」の中にある尊さを再認識させてくれる作品です。
さらに、しんのすけが大人たちを救う存在として描かれているのも印象的です。大人は時に視野が狭くなりがちですが、子どもの純粋な視点や未来への希望が、私たちを現実に引き戻してくれることがあります。
過去は美しい思い出として心に留めておくべきで、そこに戻ろうとするのではなく、その経験を糧に前を向いて生きることの大切さを伝えています。この映画は子ども向けアニメの枠を超えて、大人の心に深く響く普遍的なテーマを扱った傑作と言えます。
この映画を観た後に読みたい本
人生と幸福に関する書籍
『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健著)は、過去に囚われず「いま、ここ」を生きることの重要性を説いたベストセラー。映画のテーマと最も共鳴する一冊です。
『幸せになる勇気』(岸見一郎・古賀史健著)は、『嫌われる勇気』の続編。より実践的に、日常を大切に生きるヒントが詰まっています。
『置かれた場所で咲きなさい』(渡辺和子著)は、今ある環境で精一杯生きることの意味を優しく説いた本。ひろしたちの生き方に通じます。
親子関係と家族に関する書籍
『子どもへのまなざし』(佐々木正美著)は、子育ての名著。子どもとの日常の大切さ、親としての在り方を見つめ直せます。
『父親が子どもとがっつり遊べる時期はそう何年もない。』(布施太朗著)は、父親としての時間の大切さを実感させてくれる本。しんのすけとひろしの関係を思い起こさせます。
時間と記憶に関する書籍
『思い出のとき修理します』(谷瑞恵著)は、過去の思い出との向き合い方を描いた小説。懐かしさと前を向くことのバランスを考えさせられます。
『ツバキ文具店』(小川糸著)は、日常の小さな幸せを描いた物語。平凡な毎日の尊さを再認識できます。
基本情報
ジャンル:アニメ
公開:2001年
時間:89分(1時間29分)
監督:原恵一
原作:臼井儀人
あと、オラ大人になりたいから。大人になって、お姉さんみたいな綺麗なお姉さんといっぱいお付き合いしたいから。
野原しんのすけ
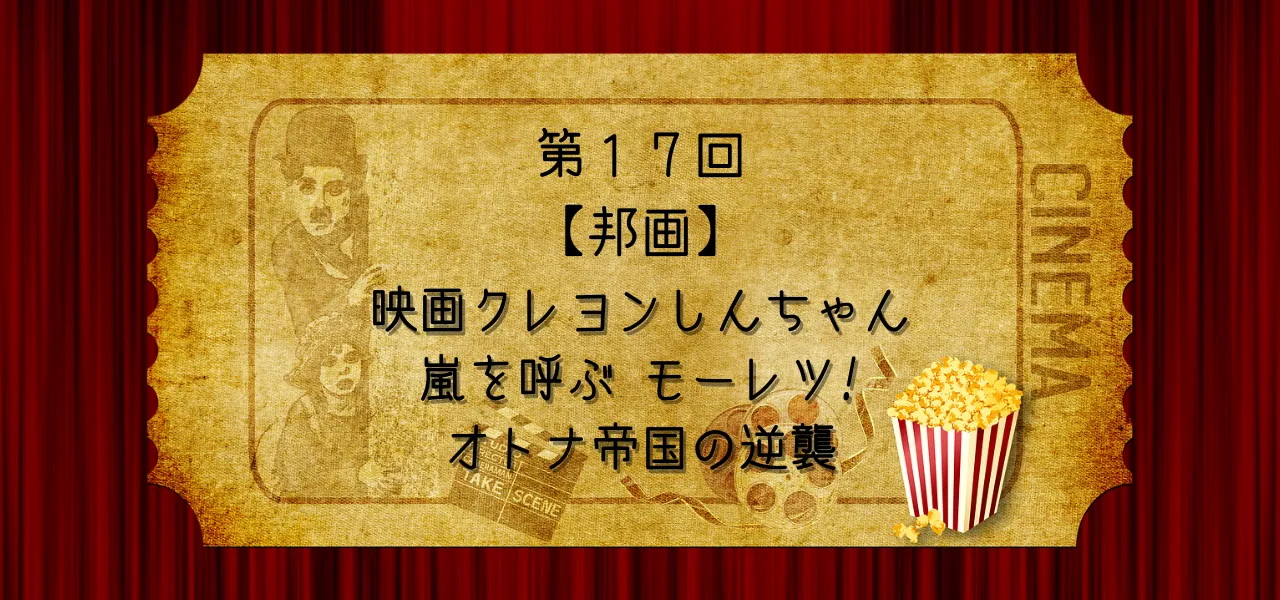
![映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲 [ 臼井儀人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9639/4934569639639.jpg?_ex=128x128)
![嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え [ 岸見 一郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5819/9784478025819.jpg?_ex=128x128)
![幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え2 [ 岸見 一郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6119/9784478066119.jpg?_ex=128x128)
![置かれた場所で咲きなさい [ 渡辺和子(修道者) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1747/9784344021747.jpg?_ex=128x128)
![子どもへのまなざし (福音館の単行本) [ 佐々木正美 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4730/9784834014730.jpg?_ex=128x128)

![思い出のとき修理します (集英社文庫) [ 谷瑞恵 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8892/9784087468892.jpg?_ex=128x128)
![ツバキ文具店 (幻冬舎文庫) [ 小川糸 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7617/9784344427617.jpg?_ex=128x128)
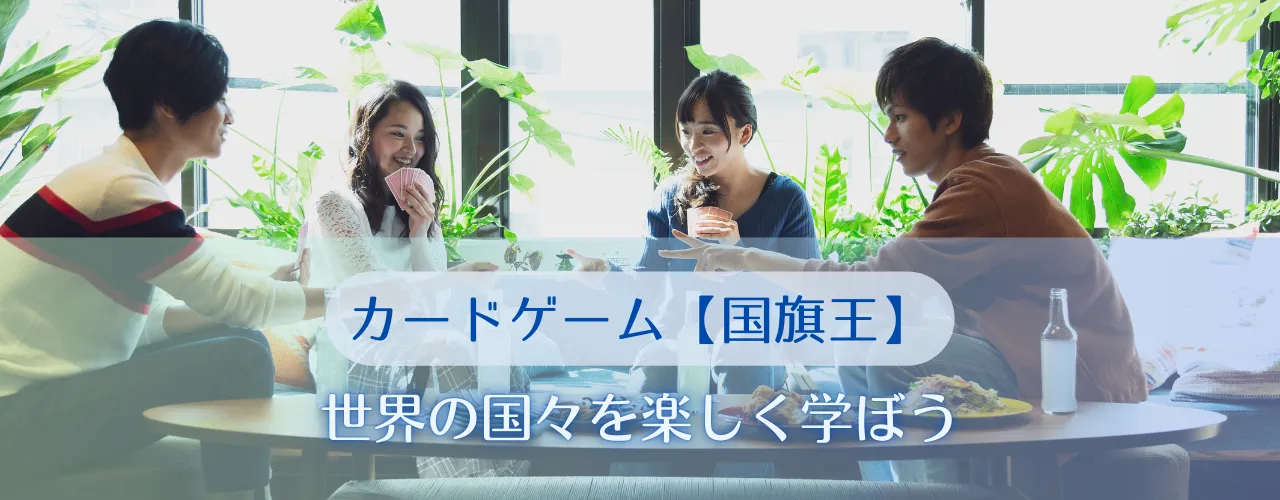

コメント